はじめに
ウルトラマラソンに挑戦した多くのランナーが経験するのが「リタイア後の後悔」です。
「仕方ないけど、まだ走れたかもしれない」──この複雑な感情は、挑戦した人にしか分からない苦さを持っています。
レース中は「もう無理だ」と強く感じてリタイアを選んだはずなのに、数時間後や翌日になると「実際には余力が残っていたのでは」と考えてしまう。
この“リタイアと後悔のギャップ”の背後には、脳が全身を守るために発動する防衛反応と、それによって引き起こされるメンタル切れが深く関わっています。
脳がかけるブレーキ──リタイアの瞬間に起きていること
ウルトラの現場では、「走れない」ではなく「走りたくない」が突然訪れます。
身体はまだ動けるのに意欲が消える。これはまさに脳が思考をジャックする状態です。
この現象の説明として知られるのが、南アフリカの研究者ティム・ノークスが提唱したセントラル・ゴヴァーナー理論です。
- 疲労は筋肉や心肺の絶対的な限界ではなく、脳が作り出す「主観的感覚」である
- 脳は体温、血糖値、循環動態などを総合し、「危険」と判断すれば運動を強制的に抑制する
- これによって身体は壊れる前に止められる
つまり、リタイアの瞬間とは「脳が早めにブレーキをかけた」結果なのです。
30kmの壁とメンタル切れは別物
マラソンやウルトラでは「30kmの壁」と「メンタル切れ」がしばしば混同されます。
しかし両者はまったく異なるメカニズムで起こります。
30kmの壁=走りたいのに走れない(身体の限界)
- グリコーゲン枯渇によるエネルギー不足
- 血糖値の低下による集中力低下
- 筋肉損傷や乳酸蓄積による脚の重さ
これは純粋に「燃料切れ」「機械的な限界」であり、補給戦略(炭水化物60〜90g/時)やペース配分である程度防げます。
メンタル切れ=走らなければいけないのに走りたいと思えなくなる(脳の限界)
- 身体にはまだ余力が残っている
- しかし脳が防衛反応を強め、意欲をシャットダウンする
- 結果として「もう走りたくない」と強烈に感じる
研究では、長時間の認知課題を課した後に持久走を行わせると、心拍や筋活動が同じでも「疲労感が強くなり、早くやめてしまう」ことが示されています。これはメンタル疲労がRPE(主観的努力感)を引き上げ、パフォーマンスを落とすという実験的証拠です。
レース後に生まれる後悔の正体
リタイア後、筋肉痛や疲労はあるものの「数日で回復した」「翌日には歩けた」という体験をしたことはありませんか?
これが「まだ走れたのでは」という後悔を生みます。
しかし実際には、脳が安全マージンを広くとって止めさせただけです。限界の手前でブレーキをかけることで、身体の中には“使われなかった余力”が残ってしまうのです。
言い換えれば、後悔は「脳が安全に働いた証拠」でもあります。
脳が思考をジャックする要因(エビデンスと解説)
高体温(ハイパーサーミア)
深部体温が上昇すると、脳は「危険信号」を発します。体温が1℃上がるごとに持久力が低下するという報告もあり、熱そのものが「つらさ」を増幅します。研究では、深部体温が40℃近くに達すると運動持続時間が急激に短くなることが示されました。
脱水
体重の2%以上の水分を失うと、心拍数が上昇し、血流が制限されます。結果として脳への血流も減少し、強い疲労感を誘発します。2〜3%の脱水で持久力低下が生じるとするレビューもあります。
低血糖
補給不足で血糖が低下すると、エネルギーだけでなく意思決定そのものが鈍ります。炭水化物を口に含むだけでも脳の報酬系が活性化し「まだいける」と感じやすくなることが報告されています。
睡眠不足
ウルトラマラソンでは夜を越えて走ることが多く、睡眠不足は強い敵になります。レビューでは、短距離のウルトラ(100マイル前後)では徹夜で走破が可能でも、200マイル級では戦略的な仮眠が不可欠だとされています。
メンタル疲労(認知的負荷)
長時間の集中や判断を伴う活動は、それ自体が「脳のエネルギー消費」となり、疲労感を増幅します。メタ解析では、精神的疲労が持久運動のパフォーマンスを確実に低下させることが示されています。
実際のウルトラマラソン事例
事例1:夜明け前のエイドで動けなくなる
午前3時、80km地点のエイド。胃の不快感と眠気でベンチから立ち上がれず、そのままリタイア。しかし数時間後には体調が戻り「あと少し頑張れたのでは」と後悔。これは低エネルギーと睡眠不足の複合による典型的なメンタル切れです。
事例2:真夏のトレイル100マイル
炎天下で発汗が激しく、体重が2%以上減少。心拍数は高止まり。脚はまだ動くが「もう無理だ」と感じてリタイア。翌日は普通に歩けてしまい「本当にやめる必要があったのか」と悔やむ。実際には高体温と脱水による強烈な防衛反応が原因でした。
安全に越したことはない
ここで大切なのは、リタイアは決して弱さではないという点です。
めまい、視界の歪み、強い吐き気、意識の混濁、胸痛といった症状が出た時点で、レースを続けるのは危険です。
脳が安全マージンを広くとってブレーキをかけるのは、命を守るために備わった合理的な仕組みです。
「もう少し走れたかも」という後悔が残っても、安全を優先した判断は正しいのです。
後悔を減らすための工夫
客観的な撤退基準を決める
「視界がかすんだら」「めまいがしたら」など、具体的に危険サインを決めておくことで、感情的に流されず冷静に判断できます。
小目標で脳をだます
「次のエイドまで」「あと1kmだけ」と短い区切りを設定することで、モチベーションを維持しやすくなります。
セルフトークで意欲を上書きする
「ここを越えれば復活する」と声に出して自分を励ます。研究でも、セルフトークがRPEを下げ、持久時間を延ばす効果が確認されています。
外部の力を借りる
ペーサーや仲間と状況を共有し、判断を二重化します。「主観的には無理」と思っても、客観的に見れば走れることもあります。
まとめ
ウルトラマラソンでリタイアを後悔するのは、多くのランナーが経験する自然な現象です。
それは脳が安全を優先してメンタルを切った結果であり、身体に余力が残っていたからこそ生じる感情なのです。
- 30kmの壁=走りたいのに走れない(身体の限界)
- メンタル切れ=走らなければいけないのに走りたいと思えなくなる(脳の限界)
この違いを理解し、補給・睡眠・セルフトーク・仲間のサポートといった対策を取り入れれば、後悔を減らし、より納得のいく挑戦ができるでしょう。
そして最後に忘れてはならないのは、「安全に越したことはない」という前提です。リタイアは命を守るための選択であり、次の挑戦へとつながるステップなのです。
参考文献
- Noakes TD. Fatigue is a brain-derived emotion. Front Physiol. 2012.
- Van Cutsem J, et al. The effects of mental fatigue on physical performance: a systematic review. Sports Med. 2017.
- Marcora SM, et al. Mental fatigue impairs physical performance in humans. J Appl Physiol. 2009.
- Jeukendrup AE. A step towards personalized sports nutrition: carbohydrate intake during exercise. Sports Med. 2014.
- Cheuvront SN, Kenefick RW. Dehydration: physiology, assessment, and performance effects. Compr Physiol. 2014.
- González-Alonso J, et al. Influence of body temperature on fatigue during prolonged exercise in the heat. J Appl Physiol. 1999.
- Chambers ES, et al. Carbohydrate sensing in the human mouth: effects on exercise performance and brain activity. J Physiol. 2009.
- Nikolaidis PT, et al. Sleep in marathon and ultramarathon runners: a brief narrative review. Front Neurol. 2023.
- Guest NS, et al. International Society of Sports Nutrition position stand: Caffeine and exercise performance. J Int Soc Sports Nutr. 2021.
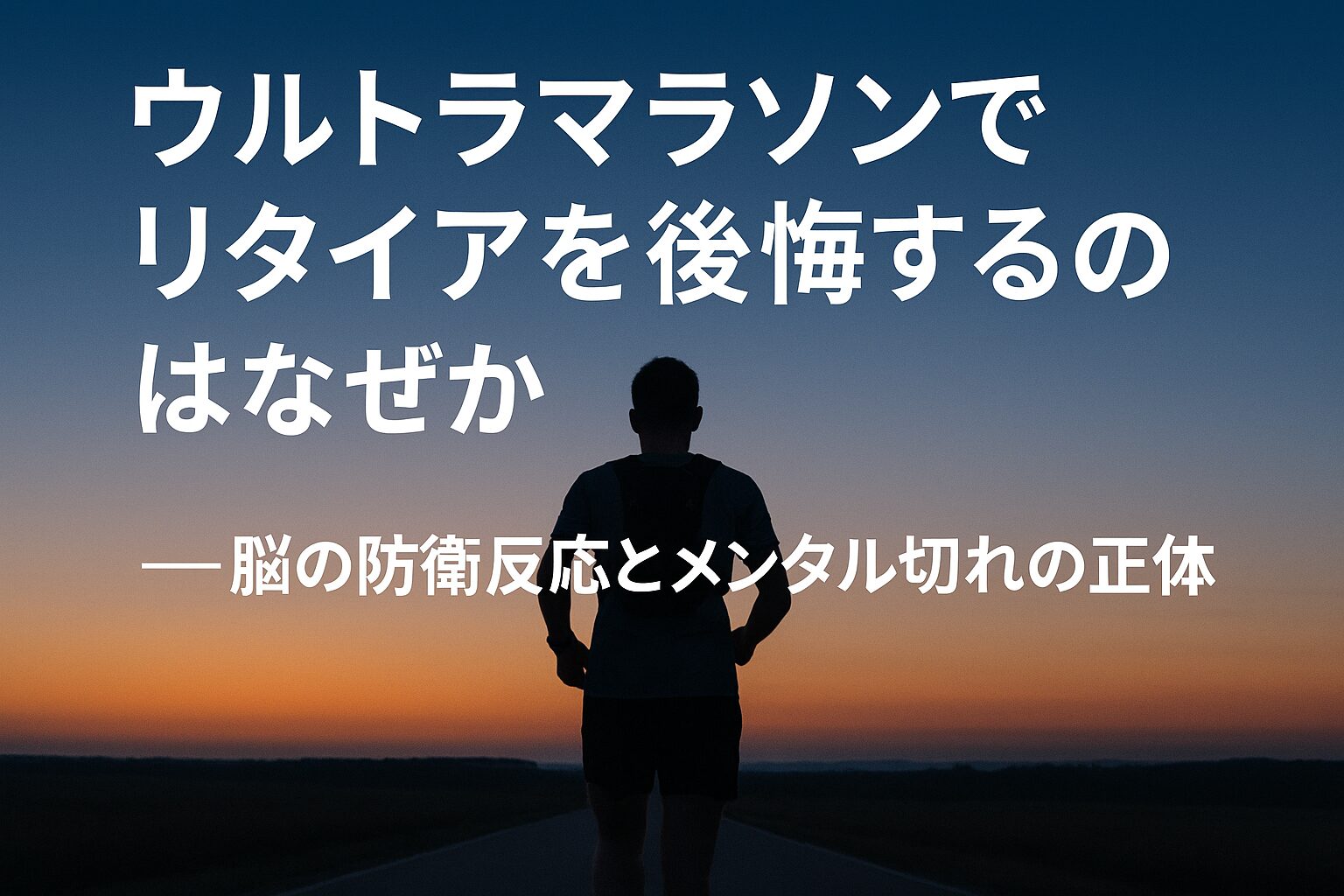


コメント