はじめに
ウルトラマラソンやフルマラソンの後半、あるいはロング走の練習中に、「もう走りたくない」「ここでやめたい」と強烈に感じる瞬間があります。これは根性の問題ではなく、科学的には脳が発する防衛反応によって意欲が遮断されている状態です。
とはいえ、実際には身体に余力が残っていることも多く、工夫次第で再び走り出せます。本記事では、メンタル切れのメカニズムを簡潔に押さえたうえで、レース中に使える立て直しテクニックを具体的に紹介します。
メンタル切れが起こるメカニズム
脳の防衛反応
脳は身体の破綻を避けるために、低血糖・脱水・高体温・疲労の蓄積などの危険信号を統合し、「やめたくなる感情」を生み出して運動を抑制します。これはセントラル・ゴヴァーナー理論で説明され、疲労は筋肉の限界ではなく脳が作り出す主観的感覚だと位置づけられています。
主観的努力感(RPE)の急上昇
メンタル切れでは、筋力や心拍が同じでもRPE(つらさ)が跳ね上がり、「動けるのにやめたい」と感じます。長時間の認知負荷やストレス、睡眠不足はRPEを押し上げることが知られています。
睡眠不足と認知的疲労
ウルトラでは徹夜や長時間走が避けられず、睡眠不足がメンタル切れを増幅します。仕事や日常ストレスによる認知的疲労も、RPE上昇と持久力低下の一因になります。
立て直しの実践テクニック
1. セルフトークで脳を書き換える
- 小目標:「あと1kmだけ」「次のエイドまで」と区切る
- 言葉の力:「ここを越えれば落ち着く」「大丈夫、整ってきている」を声に出す
- ポイント:否定語(無理・ダメ)を避け、具体的で現在形の短いフレーズを反復
2. 補給と水分で脳を安心させる
補給や水分は即効薬ではありません。消化・吸収・利用には時間がかかるため、後半に慌てて入れても間に合わないことが多いです。ゆえに序盤から計画的に少量ずつが原則です。
- 補給:30〜45分ごとに糖質を摂取(目安60〜90g/時、グルコース+フルクトース併用)
- 水分:発汗量に応じて1回100〜200mlをこまめに。体重減少2%超は失速のリスク
- 安心信号:口に含む(マウスリンス)だけでも脳の「いける」サインを引き出すことがある
3. 身体をリセットする(短時間の立て直し休憩)
- エイドで1〜2分、深呼吸をして椅子に座る
- 頸部や頭部の冷却(氷・水かぶり)、濡れた帽子・バフの活用
- ソックス・シャツの着替えで不快感を取り除く
- 再出発の合図を決めておく(タイマーや「ここから歩き1分→ジョグ3分」)
4. 睡眠・仮眠の活用(ウルトラ特有)
- 短時間仮眠:5〜20分でも意欲回復のケース多数
- 事前の睡眠貯金:レース週は睡眠時間を増やす(スリープバンキング)
- 眠気対処:安全第一。強い眠気や注意低下は早めに仮眠を入れる
5. 外部刺激で意識を切り替える
- 音楽・応援・会話で単調さを壊す
- 景色が変わる区間を区切り目にする(橋・公園・峠・街中など)
- ペーサーや仲間の一言を借りる(客観的なリズムを外から与える)
ケーススタディ:レース現場での立て直し
Case 1:100kmでのメンタル切れを10分で脱出
70km地点で「やめたい」。エイドで頸部冷却とジェル摂取、「次の5kmだけ」とセルフトーク。10分で意欲回復し完走。
Case 2:夜間の眠気でリタイア寸前→仮眠で復活
200kmレースの夜間、幻覚が出るほどの眠気。エイドで15分仮眠し、覚醒後は意欲と集中が戻り完走。
Case 3:孤独感で失速→伴走でペース再構築
後半の無人区間で気持ちが切れたが、仲間が伴走に入り「話す→笑う→走る」の流れで再加速。
レース前からの予防(切れにくい下地づくり)
練習で「脳の慣れ」を作る
- ロング走を段階的に延ばす(25→30→35km)
- 練習でも補給・水分のタイミングを本番同様に試す
- 暑熱順化(2〜3週間で汗の質・体温調節が改善)
ペース戦略(前半の欲張りを封じる)
- ネガティブスプリットかイーブンを想定
- 心拍ゾーン・RPEを指標に余裕を残す
- 下り・追い風・日陰で「楽に稼ぐ」、登り・向かい風・日向で「削らない」
補給・水分の「前倒し設計」
- 開始30〜45分で1回目、その後も機械的に継続
- 糖質60〜90g/時(グルコース+フルクトース併用)、ナトリウム適量
- 1回100〜200ml、水とスポドリを状況で使い分け
よくある誤解とQ&A
Q. 30kmでジェルを2個取れば復活しますか?
A. その場で即効は期待できません。吸収には時間がかかるため、序盤からの計画的摂取が重要です。
Q. 喉が渇いてから飲めば十分?
A. 渇きはすでに遅れ気味のサイン。吸収のタイムラグを考え、こまめに前倒しで補給を。
Q. 一度止まったら終わり?
A. 短時間の立て直し休憩で再出発できる例は多数。「止まってもまた走れる」経験を練習で作っておきましょう。
まとめ
- メンタル切れは脳の防衛反応。身体に余力が残るケースは多い
- 立て直しはセルフトーク/補給・水分の前倒し/短時間リセット/仮眠/外部刺激が柱
- 予防は練習での慣れ・暑熱順化・無理のないペース設計から
メンタル切れは誰にでも訪れます。しかし、適切な知識と道具立てがあれば、リタイアの危機を「再出発のきっかけ」に変えられます。
参考文献
- Marcora SM, et al. Mental fatigue impairs physical performance in humans. J Appl Physiol. 2009.
- Van Cutsem J, et al. The effects of mental fatigue on physical performance: a systematic review. Sports Med. 2017.
- Chambers ES, et al. Carbohydrate sensing in the human mouth: effects on exercise performance and brain activity. J Physiol. 2009.
- Blanchfield AW, et al. Self-talk improves endurance performance. Med Sci Sports Exerc. 2014.
- Nikolaidis PT, et al. Sleep in marathon and ultramarathon runners: a narrative review. Front Neurol. 2023.
※ 医学的助言ではありません。めまい・視界異常・胸痛・強い吐き気などの異常があれば直ちに中止し、医療者の指示に従ってください。
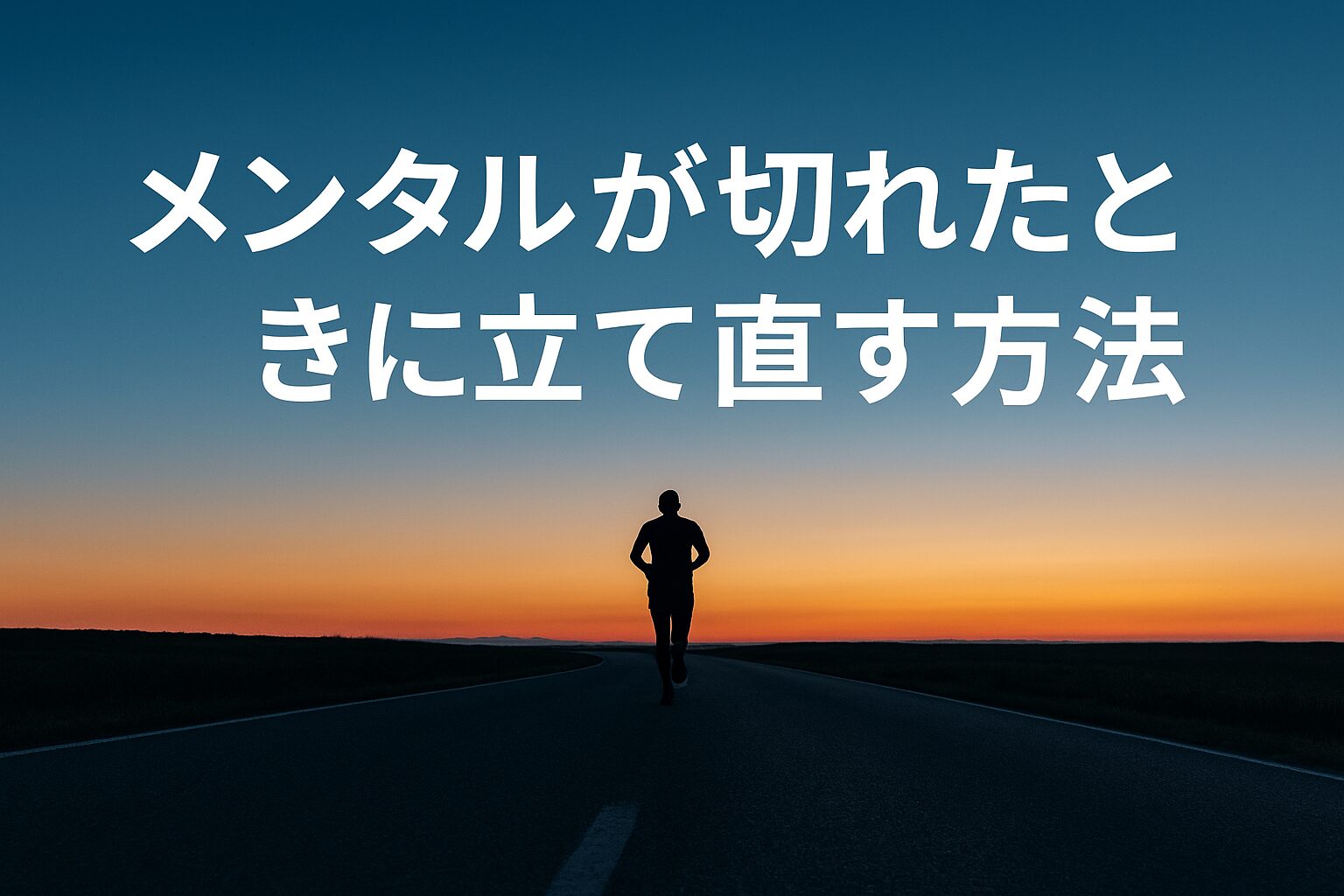

コメント