はじめに
ウルトラマラソンやロングトレイル、長時間にわたる山岳レースなど、10時間以上に及ぶ持久系スポーツでは、発汗による脱水と適切な水分補給のバランスが非常に重要になります。
特に夏場や高湿度環境下では、体温調節のために大量の汗をかきます。では、「どのくらい汗をかいて、どのくらい飲めば良いのか?」「体は1時間にどれくらい水分を吸収できるのか?」「どんな運動強度が理想的か?」といった疑問を、紐解いていきます。
1. 発汗量と運動強度の関係
▶ 最大心拍数と相対的運動強度
まず基本として、「最大心拍数(HRmax)」はおおよそ以下の式で推定できます:
最大心拍数 ≒ 220 − 年齢
この心拍数に対して、実際の運動中の心拍数が何%かで運動強度を表します。
| 運動強度 | 心拍数(%HRmax) | 主な活動内容 |
|---|---|---|
| 低強度 | ~50% | ウォーキング |
| 中強度 | 50~70% | LSD走・登山 |
| 高強度 | 70%以上 | インターバル・スピード走 |
ここで重要なのは、発汗量は運動強度に比例するということ。
気温や湿度が一定と仮定すると、心拍数が高くなるほど体温も上がり、発汗量も増加します。
2. 発汗量の目安と体重
発汗量は体格によっても変わります。目安としては以下の通り:
発汗量:0.8〜1.4L/時(体重65kgで中〜高強度運動時)
これは環境にもよりますが、たとえば1時間で体重の1%(=約650g)の汗をかくというのは実際のデータでもよく見られます。
3. 水分補給の吸収限界
▶ 腸管で吸収できる水分の上限
重要なのは「どれだけ飲めるか」ではなく「どれだけ吸収できるか」。
腸管での水分吸収上限はおおよそ 600〜800ml/時
高張液や冷たい水では吸収効率が落ち、胃に滞留するリスクも。さらに発汗による水分喪失が1000ml/時に近づくと、吸収と排出のバランスが崩れ、脱水症状のリスクが高まります。
4. 長時間レースにおける実際のバランス
💡 ケース:65kgの選手が10〜20時間走る場合
仮に毎時0.7Lの汗をかいたとすると、10時間で7L、20時間で14Lの水分を失う計算です。
腸で吸収できるのは多くて800ml/時、つまり:
- 最大で吸収できる水分:10時間で8L、20時間で16L
この数字を見る限り、理論的には「水分補給で帳尻は合わせられる」ようにも思えます。
しかし、これはあくまで理論上。実際には、
- 胃腸の疲労による吸収低下
- 飲水タイミングのズレ
- 食事による水分ロス
- 塩分・糖分による吸収スピードの変化
などの要因が絡み、毎時間800mlを安定して吸収することは困難です。
5. 現実的な戦略:運動強度を落とすという選択
吸収と発汗のバランスを保つには、発汗量そのものをコントロールする必要があります。
そのためには:
- ✅ 運動強度を50%HRmax以下に落とす(歩くことを含める)
これは身体の水分消費を抑え、腸の吸収能力に見合った給水量で収まるようにするための工夫です。
また、気温の高い昼間は抑え、夜間や標高の高い涼しい場所でペースを上げるなど、温度変化を戦略に組み込むのも効果的です。
さらに、50〜60%の低強度を維持していくのが望ましいですが、関門時間や温度や湿度、走力などのさまざまな要素で難しい局面もあります。
そういうときも歩きを意図的に入れて平均的な運動強度を下げるという戦略も取れると思います。
6. ハンガーノックだけではない、脱水のパフォーマンス低下
脱水症状が進行すると、パフォーマンスが著しく低下します。
| 脱水率(体重比) | 症状 |
|---|---|
| 1~2% | 体温上昇、パフォーマンスの低下 |
| 2~3% | めまい、吐き気、筋肉けいれん |
| 4%以上 | 重度の集中力低下・リスク行動増加 |
多くのウルトラランナーは「食べられない・飲めない」タイミングを迎えますが、これは胃腸機能の低下が原因であり、そのきっかけが発汗と補給のアンバランスであることも少なくありません。
7. 超長距離での実践ポイントまとめ
| 項目 | 推奨戦略 |
|---|---|
| 運動強度 | 50%HRmaxを目安、登りや暑い時間帯は歩く |
| 水分補給量 | 1時間あたり600~800mlまで |
| 発汗抑制の工夫 | 涼しい服装・ネッククーラー・帽子など |
| 補給タイミング | こまめに少量ずつ、胃を一度に使わない |
| 塩分(電解質)補給 | Na濃度0.5~0.7%のスポーツドリンクを使用 |
おわりに:完走への鍵は「ゆっくり、たっぷり、慎重に」
長時間の耐久レースでは、走力だけではなく、「補給力」と「計画性」が完走を左右します。
汗の量を知り、水分の吸収上限を知り、運動強度とペースの調整を行うことは、決して後ろ向きな戦略ではなく、完走するための前向きな戦術です。
ゆっくり走る。歩く。休む。そしてまた前に進む。
もちろん、関門や制限時間に間に合わせないといけないので、急ぐところは急ぐ必要がありますし、地形やコンディションなど思うように理想通りに行かないことがたくさんあると思います。
競技時間によってはゴールに合わせてスタミナを使い切る戦法も有効です。
あくまで今回の話は20時間やさらにそれ以上を脱水などでリタイアせずに完歩するための戦略のひとつとして参考になればと思います。
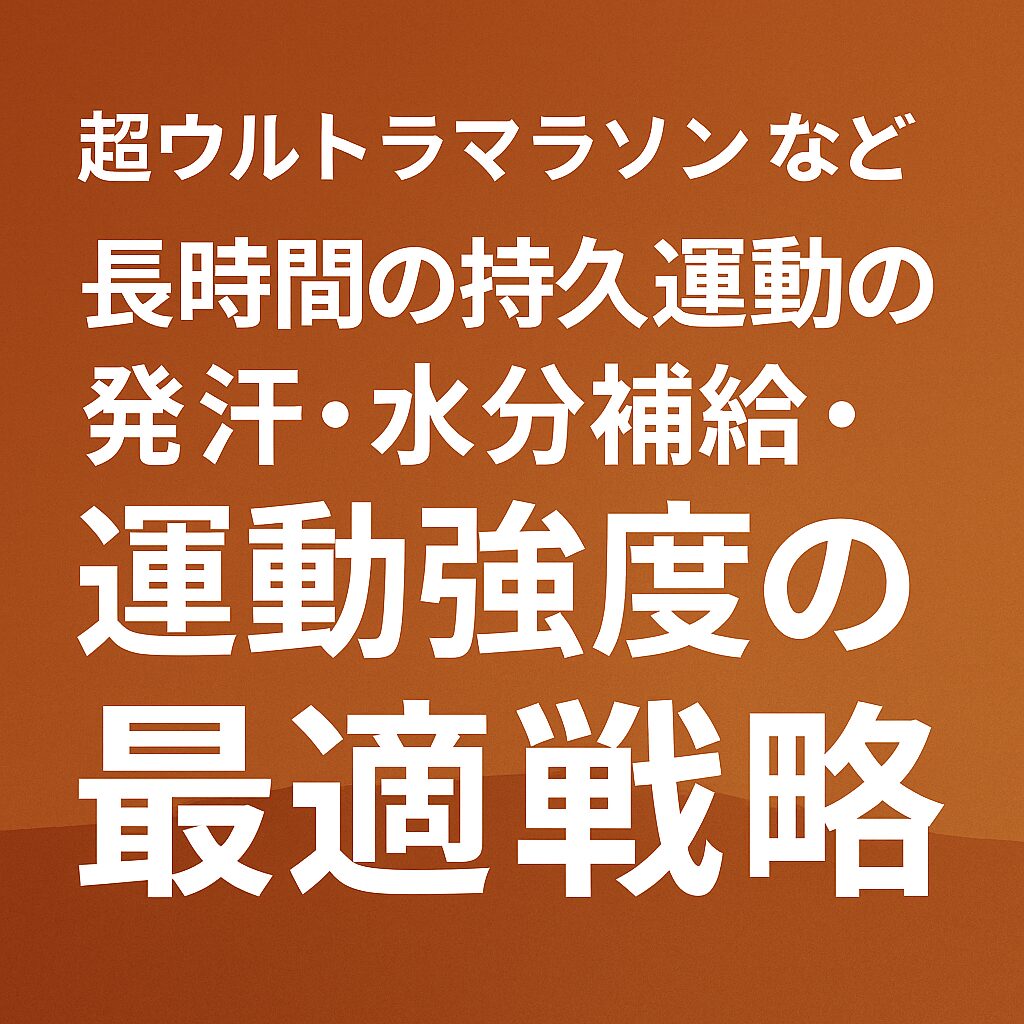

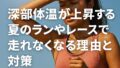
コメント