近年、催涙スプレーの所持は広がる一方、誤噴射や衝動的使用によるトラブルも増加。渋谷の商業施設、ショッピングモール、小学校、駅ホームなどでの事例が象徴的です。最大の論点は「事が起きてからでは遅い」。本稿では、事件・背景・法的留意点を整理しつつ、予防→察知→最後の手段の多層防御で向き合う実践策を提示します。
近年の事例──公共空間で広がる誤使用と衝動噴射
ここ数年、催涙スプレー(護身用スプレー)に関連するトラブルが多様な場所で報じられています。象徴的なのは、大型商業施設・ショッピングモール・学校・駅ホームといった「人が密集する場所」での誤使用・衝動噴射です。
- 都市の大型商業施設:館内で噴射され、多数が目・喉の痛みを訴える事例。意図的・悪質ケースだけでなく、口論の延長で衝動的に用いられることも。
- ショッピングモール:飲食エリアでのトラブルから噴射に至り、周囲の不特定多数が被害を受ける「大量被害化」の懸念。
- 学校(誤噴射):防犯目的で用意したスプレーが、管理不十分や扱いミスで児童・生徒に影響する逆転現象。
- 駅ホーム(興味本位):「どんなものか試したくて」噴射し、近くの利用者が体調不良を訴える等。携帯容易性と興味本位が結びつく危険。
これらは、個人の護身を想定した道具が、公共の安全を脅かす結果にもなり得るという二面性を示しています。
なぜ一般人が携帯するのか──不安・制度・市場
1) 事件報道と「身近な不安」
通り魔や無差別攻撃は稀発でも、可視化が強く心理的影響が大きい出来事です。SNSや速報性の高い報道が重なり、実際以上に「危険が常在する」感覚が醸成されます。痴漢・ストーカー被害、帰宅時の不安など、属性特有の脆弱性も携帯意欲を高めます。
2) 公的治安への信頼揺らぎ
地方での交番統廃合や人員配置の制約などから、「助けがすぐ来るとは限らない」という現実が認識され、自己防衛志向が強まりました。
3) 市場拡大と入手の容易さ
ネット通販や専門店で容易に購入でき、マーケティングは「小型・軽量・強力・安心」を訴求。結果として心理的ハードルが低下し、携帯が一般化します。
護身グッズの内在リスク──法・運用・心理
- 法的リスク:所持自体は原則違法でなくても、使用が正当防衛を逸脱すれば暴行・傷害に問われる可能性。状況(危険の程度、回避可能性、過剰性)で判断が分かれるため、安易な使用は厳禁。
- 運用上の限界:屋外では風向きにより自分や同伴者へ逆流(いわゆる「ブーメラン効果」)。密閉空間では自他ともに曝露しやすい。
- 即応性の錯覚:不意打ちケースでは、取り出す前に制圧されることも。携帯=安全ではない。
- 心理の過信:「持っているから大丈夫」という油断は、むしろ危険地帯や時間帯の行動選択を甘くし、リスクを増幅。
- 管理リスク:家庭・学校・公共施設での保管・管理不備が誤噴射に直結。
「事が起きてからでは遅い」への応答──多層防御
最大の矛盾は、護身具が攻撃開始後にしか使えない点です。不意打ちが多い現実を踏まえると、真に重要なのは起きる前に避けること。そこで次の三層モデルで考えます。
- 第1層:予防(Avoid)──環境と行動で「出会わない」
・夜は明るく人通りの多い道を選ぶ/人気のない近道を避ける
・ながら歩き(イヤホン・画面注視)を控え、周囲360°へ定期スキャン
・「つけられている感覚」があれば立ち止まり、店舗・駅・交番に入る - 第2層:察知・威嚇(Deter/Detect)──早期に「引かせる」
・大音量の防犯ブザー、強力ライト(顔面直視を避け照らす)
・人目のある場所へ移動し、声を出す/通報する体制を整える - 第3層:最後の手段(Last resort)──避けられないとき
・催涙スプレーは退避の時間稼ぎのための最終手段と位置づける
・屋外では風向・距離、屋内では自他曝露を即時に想定し、噴射後は即離脱
実践チェックリスト──今日から変えられること
- 通勤・帰宅ルートを再設計:明るさ・人通り・逃げ込み先(コンビニ等)を地図上で可視化。
- ながら歩きゼロ宣言:イヤホンは片耳・音量低め、または外す習慣。
- 防犯ツールの優先順位:ブザー&ライトを標準装備。スプレーは最後の手段と明確化。
- 取り出し動線:カバンの定位置/すぐ掴めるポケットに固定(がさごそ探す時点で負け)。
- 「声に出す」練習:助けを呼ぶフレーズを決め、実際に小声で練習しておく。
- 家族・学校・職場の保管ルール:鍵付き・子どもの手の届かない場所/管理者の明確化。
ミニFAQ──よくある疑問
Q. 所持は違法ですか?
A. 日本では一般に所持自体は直ちに違法ではありませんが、使用が正当防衛を外れると犯罪に問われ得ます。状況判断が厳しく問われるため、安易な携帯・使用は避けましょう。
Q. 飛行機やイベント会場に持ち込めますか?
A. 多くの航空会社・空港、イベント会場では持込禁止です。移動前に必ず規約・持込制限を確認してください。
Q. 屋外での使用は安全ですか?
A. 風向・距離次第で自分に逆流するリスクが高く、屋内では自他ともに曝露します。噴射は退避の時間稼ぎに徹し、即離脱が原則です。
おわりに──安心を回復するために
催涙スプレーの普及は治安崩壊の証ではなく、安心感の低下の表れです。だからこそ、個人は「予防→察知→最後の手段」の多層防御で日常を守り、社会は街灯・見守り・迅速対応などのインフラで起きる前に避ける仕組みを整える必要があります。護身具は最後の砦。日々の安全は、環境デザインと私たちの行動がつくります。
免責:本記事は一般的情報提供であり、法的助言・専門的助言ではありません。具体的判断は各機関・専門家にご相談ください。
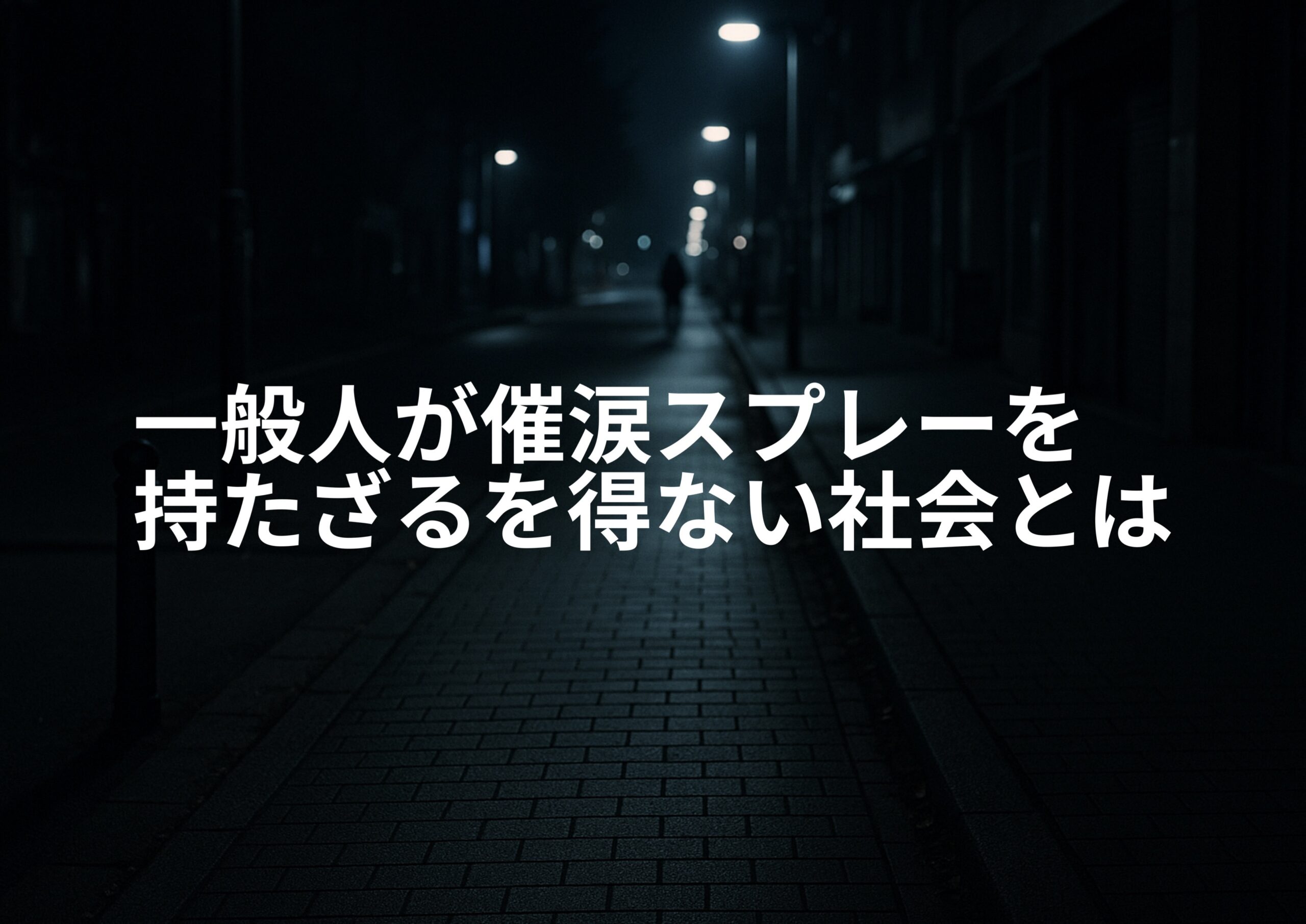
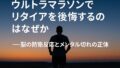

コメント