「もっと脂肪を燃やせる体にしたい」「マラソンやウルトラで長時間走り切りたい」──そんなときにカギになるのがMFO(最大脂肪酸化速度)とファットアダプテーションです。
従来は「糖を節約する」という言い方をされることが多いのですが、ウルトラランナーの本音は『糖を同じ運動強度でも糖に過度に頼らず、脂肪をより効率的に使える体にしたいという前向きな発想です。
こうした「代謝の柔軟性」を高めることこそが、長時間の競技で最後まで安定して走り続けるカギになります。
MFOとファットアダプテーションとは?
MFO(最大脂肪酸化速度)
MFOとは、運動中に1分あたりで最も多く脂肪をエネルギーとして使える速度のことです。単位はグラム/分。
一般人では0.3〜0.5 g/分程度、持久系アスリートでは0.8〜1.0 g/分以上に達することがあります。
数値が高いほど「長時間の運動を脂肪中心でまかなえる」=「糖を温存できる」ため、スタミナ維持に有利です。
ファットアダプテーション(Fat Adaptation)
ファットアダプテーションとは、食事や運動の工夫によって「体が脂肪を優先的に使う能力」を高めた状態を指します。
筋肉内のミトコンドリアや脂肪酸を運び込む輸送たんぱくが増え、脂質代謝酵素も活発化。結果として同じ強度でも糖ではなく脂肪を効率的に使えるようになります。
エリート選手やウルトラランナーの中には、ファットアダプテーションを経てMFOが1.5 g/分に達した例もあります。
ただしメリットだけではありません。脂肪利用は増えますが、高強度でのパフォーマンスは落ちやすいため、期間限定や戦略的な導入が必要です。
食事と運動によるMFO向上の組み合わせ
A. MFOを本当に高める組み合わせ
1. Zone2有酸素+継続的トレーニング
最も確実なのは、週に複数回の有酸素運動を継続すること。
研究では、ミトコンドリアや脂質代謝酵素の増加によって、MFOが着実に上昇することが示されています。
「脂肪を燃やす工場をコツコツ増やす」イメージです。
2. 空腹運動(fasted training)や“sleep-low”戦略
糖質が少ない状態で運動すると、体は「脂肪を使わざるを得ない」モードに切り替わります。
例えば「夜に糖質を抑えて寝て、翌朝に走る(sleep-low)」と、脂肪燃焼関連の遺伝子が強く働きます。
これにより、MFOと持久力の両方が向上するケースが確認されています。
3. 低糖質高脂肪食(LCHF/ケトジェニック)+有酸素
数日〜数週間のLCHF食は、MFOを0.6→1.3 g/分級にまで高める効果が報告されています。
これは「脂肪エンジンに強制切り替え」する強力な手段。ただし高強度運動では酸素コストが増え、スピードが出にくくなるため、ベース期限定で導入し、レース期には炭水化物を戻すのが現実的です。
B. 効果が限定的な組み合わせ
4. カフェイン+有酸素
カフェイン摂取で脂肪酸が血中に動員され、MFOがわずかに上がります。
ただし効果は小さく個人差も大きいため、「脂肪燃焼のブースター」というよりは「集中力や疲労感軽減」の方が実用的です。
5. MCTオイル+有酸素
中鎖脂肪酸(C8/C10)はすぐに燃料化されますが、MFOの「最大値」を大きく変えるほどではありません。
「即効エネルギー」としては使えますが、消化器トラブルが起きやすいため、実戦投入には注意が必要です。
C. MFO目的では避けたい組み合わせ
6. 運動直前の糖質摂取
運動前に炭水化物を食べるとインスリンが分泌され、脂肪利用が抑制されます。その結果、MFOは約30%低下。
脂肪燃焼を目的とするセッションでは、直前の糖質は控えるのが賢明です。
7. ココナッツオイル
ココナッツオイルの主成分ラウリン酸(C12)は「MCT」と呼ばれますが、実際の代謝は長鎖脂肪酸に近く、MFO向上を示すデータはありません。
「MCT=ココナッツオイル」という誤解には注意が必要です。
8. 外因性ケトン
ケトンサプリを摂取すると血中ケトンは増えますが、脂肪酸酸化はむしろ下がりやすい傾向が報告されています。
「ケトンを飲めば脂肪が燃える」というのは誤解であり、MFO目的では逆効果になり得ます。
ファットアダプテーションを活かす実戦的プロトコル
- ベース期: 低糖質やsleep-lowを取り入れて「脂肪エンジン」を鍛える
- レース前期: 炭水化物を再導入して「糖エンジン」も回復
- レース本番: 両方のエンジンを使える状態で臨む
つまり「糖を節約する」よりも、同じ強度で脂肪を効率的に使える体をつくることが最重要です。これこそが、ウルトラランナーが目指すべき真のファットアダプテーション戦略です。
実践例:ファットアダプテーションのための1週間メニュー
ここではベース期(持久力の土台を作る時期)と、レース前期(スピードと実戦対応を重視する時期)の2パターンを紹介します。
ウルトラランナーやマラソンランナーが「脂肪を効率的に使える体」を作りつつ、「高強度にも対応できる体」を整えるための参考プランです。
1. ベース期(脂肪エンジンを鍛える時期)
| 曜日 | 内容 | 食事の工夫 |
|---|---|---|
| 月 | 休養または30分ジョグ | 通常食(中〜高糖質) |
| 火 | 朝:空腹で60分Zone2 夜:軽い補強運動 |
朝は糖質なしで開始、昼以降はバランス食 |
| 水 | インターバル(LT〜VO₂max強度) | 前後で十分な糖質補給 |
| 木 | 90分Zone2(sleep-low戦略:前夜糖質少なめ) | 夜は低糖質、翌朝空腹で開始 |
| 金 | 休養またはゆるジョグ | 通常食 |
| 土 | LSD(2〜3時間、脂肪燃焼重視) | 朝は糖質少なめ、補給は水・電解質メイン |
| 日 | テンポ走(レースペース付近) | 前日から糖質補給、実戦感覚を養う |
ポイント:
・週2〜3回「低糖質条件」での有酸素を入れて脂肪酸化能力を鍛える
・週1回は高強度+糖質補給で「糖エンジン」も刺激
・長距離走は脂肪利用を意識して補給は最小限にする
2. レース前期(スピードと実戦対応を整える時期)
| 曜日 | 内容 | 食事の工夫 |
|---|---|---|
| 月 | 休養または30分ジョグ | 通常食(高糖質寄り) |
| 火 | インターバル(LT走や5分×5本など) | 前後で糖質をしっかり摂取 |
| 水 | 60分ジョグ(Zone2) | 通常食、空腹実施は控える |
| 木 | テンポ走(マラソンペース〜やや上) | 前夜・朝に糖質を十分補給 |
| 金 | 休養またはクロストレーニング | 通常食 |
| 土 | LSD(3時間、補給を実戦通りに) | 補給食やジェルをレースと同じタイミングで摂取 |
| 日 | ビルドアップ走や30km走 | レースを想定して前日からカーボローディング気味 |
ポイント:
・レース期は糖質をしっかり戻して高強度のパフォーマンスを確保
・低糖質戦略は減らし、「両方のエンジン」を使える状態に仕上げる
・週末の長距離はレース補給のリハーサルを兼ねる
まとめ
ベース期=脂肪エンジンの強化
レース前期=糖エンジンの回復と実戦シミュレーション
この二段構えで「同じ強度でも糖に頼らず脂肪を効率的に使える体」を作りつつ、レース本番でのスピードと粘りを両立できます。
MFOを高める方法はサプリや油に頼るのではなく、食事と運動をどう組み合わせるかで決まります。
- 最優先は有酸素トレーニングの継続
- 部分的に空腹運動やsleep-lowを導入
- ベース期にはLCHFも検討し、レース期には糖質を戻す
- カフェインやMCTは補助的に活用可能
- 直前糖質・ココナッツオイル・外因性ケトンは避ける
「糖を節約する」という守りの発想ではなく、脂肪を攻めのエネルギー源として引き出すこと。これがウルトラランナーの持久力を根本から強くします。
参考文献
- Burke LM, et al. Low-carb high-fat diet in elite race walkers. J Physiol. 2017.
- Achten J, et al. Pre-exercise carbohydrate reduces fat oxidation. J Appl Physiol. 2003.
- Marquet LA, et al. Sleep-low strategy improves training adaptation. Eur J Appl Physiol. 2016.
- Yin F, et al. Endurance training increases MFO: meta-analysis. 2023.
- Dayrit FM. The properties of lauric acid in coconut oil. 2015.
- Systematic reviews on MCT, caffeine, exogenous ketones.
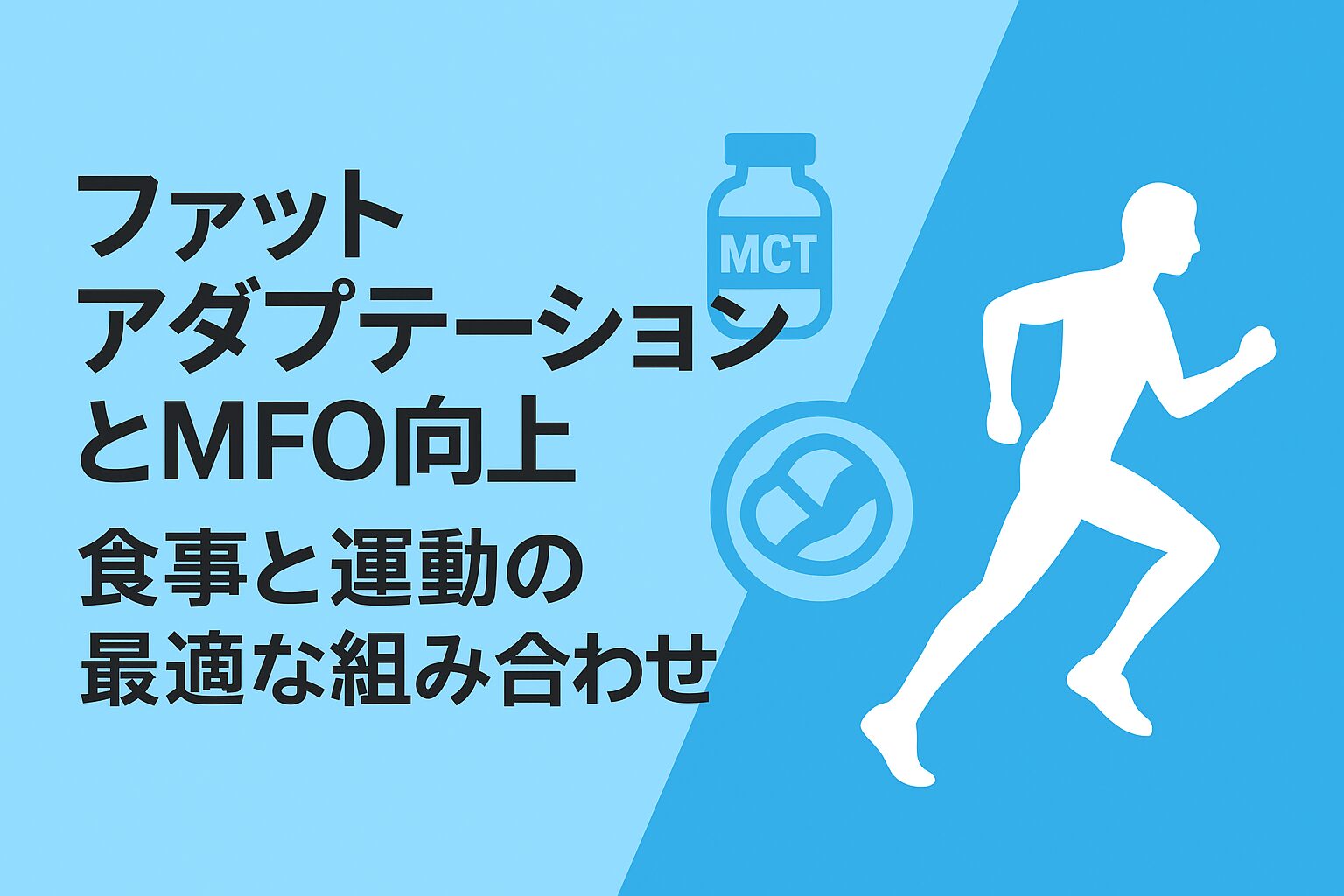

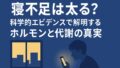
コメント