はじめに
マラソンやウルトラマラソンを走っていると、「もう無理だ」「足が動かない」と突然感じる瞬間があります。多くのランナーは「筋肉や心臓が限界だから仕方ない」と考えがちですが、実はその「限界」は、身体そのものではなく脳が作り出す感覚によるものだと考えられています。
この考え方を提唱したのが南アフリカの研究者ティム・ノークスであり、彼の唱えるセントラル・ゴヴァーナー理論(Central Governor Model, CGM)は、持久系スポーツにおける疲労の正体を解き明かす重要な鍵とされています。本記事では、この理論の概要とエビデンス、脳が限界を作る仕組み、そして実際のランニング・ウルトラマラソンにどう応用できるのかを解説します。
セントラル・ゴヴァーナー理論とは
セントラル・ゴヴァーナー理論は、従来の「筋肉や心肺が疲れ果てて動けなくなる」という理解に異議を唱えた概念です。脳は「統制者」として身体を守り、体温上昇・血糖低下・循環不全などが致命的に達する前に「疲労感」という情動を生み出し、運動強度を下げさせたり、最終的にはストップさせます。つまり、疲労は筋肉の破綻ではなく脳が発する防衛信号という位置づけです。
脳が作る「限界」の実験的証拠
メンタル疲労とパフォーマンス
メンタル疲労(注意・抑制などの認知タスクで頭を酷使した状態)は、心拍や筋力が同等でも主観的努力感(RPE)を押し上げ、運動継続時間や自己選択ペースを低下させることが繰り返し示されています。代表研究では、認知課題後にサイクリングの継続時間が有意に短縮し、被験者は「つらさ」を強く訴えました。これは疲労の決定因が筋肉ではなく“脳が作る感覚”であることを裏づけます。
炭水化物マウスリンスの効果
糖質溶液を口に含んで吐き出すだけでも、脳の報酬系が活性化し、短時間の持久パフォーマンスが改善することが報告されています。体内に吸収しなくても効果が出るのは、「脳がいける」と判断すれば身体は動けることを示唆します。
これについては、私も似たような経験があります。
ある酷暑のフルマラソン。気温に合わないペースで突っ込んでしまい、相対的にオーバーペースとなってしまいました。
当然ながら失速してしまい、もう走れないと思いリタイアを決断しました。
エイドにてリタイアを報告して、回収車を待っていたのですが、だいぶ時間がかかるとのことで諦めてゆっくり走ってゴールへと向かうことにしました。
出掛けにエイドからチョコレートをいただき、ゆっくり走っているうちに、段々と走れるようになって、そのまま元々のペースには及ばないものの、ある程度ペースを回復してゴールすることができました。
糖分によって脳がいけると判断したことによって身体が動いたということの実体験と言えると思います。
暑熱と脳のブレーキ
深部体温が上がると持久力は急落します。炎天下での運動では40℃近い深部体温に迫る前に、脳は強力なストップ信号を出します。これは、身体の破綻に至る前に安全マージンを残して止める脳の仕組みを反映しています。https://hobbyistman.com/summer-coretemp-run/
セルフトーク(自己対話)による改善
「次のエイドまで」「ここを越えれば復活する」といったポジティブなセルフトークは、RPEを低下させ、持久時間を延長することが実験で示されています。言葉で脳の信号に割り込むイメージです。
なぜ脳はブレーキをかけるのか
理由は明快で、生命を守るためです。高体温(熱中症回避)、低血糖(意識障害回避)、脱水(循環不全回避)、過度の筋損傷(長期ダメージ回避)などのリスクを未然に避けるため、脳は“壊れる直前”ではなく“壊れる前”にブレーキをかけます。ゆえにゴール後に「まだ余力があったのでは」と感じやすいのです。
30kmの壁やメンタル切れとの関係
30kmの壁はグリコーゲン枯渇・筋損傷・低血糖といった身体要因が中心で、「走りたいのに走れない」状態。一方でメンタル切れは、脳の防衛反応により「走らなければいけないのに走りたいと思えない」状態で、心理要因が中心です。両者は連続的に絡み合い、30kmの壁を超えた先には脳が作る限界との戦いが待っています。
限界を超えるための戦略(エビデンスに基づく)
補給と水分戦略
運動中の炭水化物摂取は、一般に2〜3時間のエンデュランスで60 g/時、ウルトラ規模ではグルコース+フルクトース併用で最大90 g/時を目安とします。脱水は体重の2%以内に抑えるのが基本。低血糖・脱水を防げば、脳の防衛信号を弱めてRPEの暴騰を抑えられます。
冷却対策
頸部・頭部の冷却(氷嚢・水かぶり)、衣類や帽子の工夫、日射回避は有効です。高体温そのものが「もう無理」を増幅させるため、暑熱下では冷却=脳への安心材料と考えます。
セルフトークと“小目標”
「次の1kmだけ」「次のエイドまで」など達成可能な小目標に分解し、ポジティブなセルフトークで追走します。RPEは文脈と意味づけで変わるため、言葉の選び方が効きます。
睡眠戦略(ウルトラ特有)
100マイル前後なら徹夜で押し切れる場合もありますが、200マイル級では短時間の仮眠が不可欠。レース週に睡眠を増やすスリープバンキングや、夜間に数分〜20分の仮眠を挟む戦略が現実的です。
実際の事例
事例1:夜間走での眠気と意欲喪失
100kmレースで徹夜を経験したランナーが、夜明け前に「もう走りたくない」と強烈に感じて座り込む。数十分の仮眠と温かい補給で復帰できたのは、睡眠不足による脳の防衛反応に的確に対応できたため。
事例2:真夏のトレイルでの高体温
炎天下で深部体温が上がり、脚は動くのに「危険だ」という感覚で意欲喪失。エイドで頸部冷却・水かぶり・電解質補給を徹底すると復活。熱が脳のブレーキを強めていた典型例です。
まとめ
限界は筋肉や心臓ではなく脳が作る感覚によって決まります。セントラル・ゴヴァーナー理論は「疲労=脳の防衛反応」という視点を与え、対策としては補給・冷却・睡眠・セルフトークがカギとなります。根性で押すのではなく、脳のメカニズムを理解して味方につけることが、安全に記録を伸ばす最短ルートです。
参考文献
- Noakes TD. Fatigue is a brain-derived emotion. Front Physiol. 2012.
- Marcora SM, et al. Mental fatigue impairs physical performance in humans. J Appl Physiol. 2009.
- Van Cutsem J, et al. The effects of mental fatigue on physical performance: a systematic review. Sports Med. 2017.
- Chambers ES, et al. Carbohydrate sensing in the human mouth: effects on exercise performance and brain activity. J Physiol. 2009.
- González-Alonso J, et al. Influence of body temperature on fatigue during prolonged exercise in the heat. J Appl Physiol. 1999.
- Blanchfield AW, et al. Self-talk improves endurance performance. Med Sci Sports Exerc. 2014.
- Nikolaidis PT, et al. Sleep in marathon and ultramarathon runners: a narrative review. Front Neurol. 2023.
※ 本記事は医学的助言ではありません。レース中の体調異常(意識混濁、視界異常、胸痛、ふらつき等)があれば直ちに中止し、医療者の指示に従ってください。
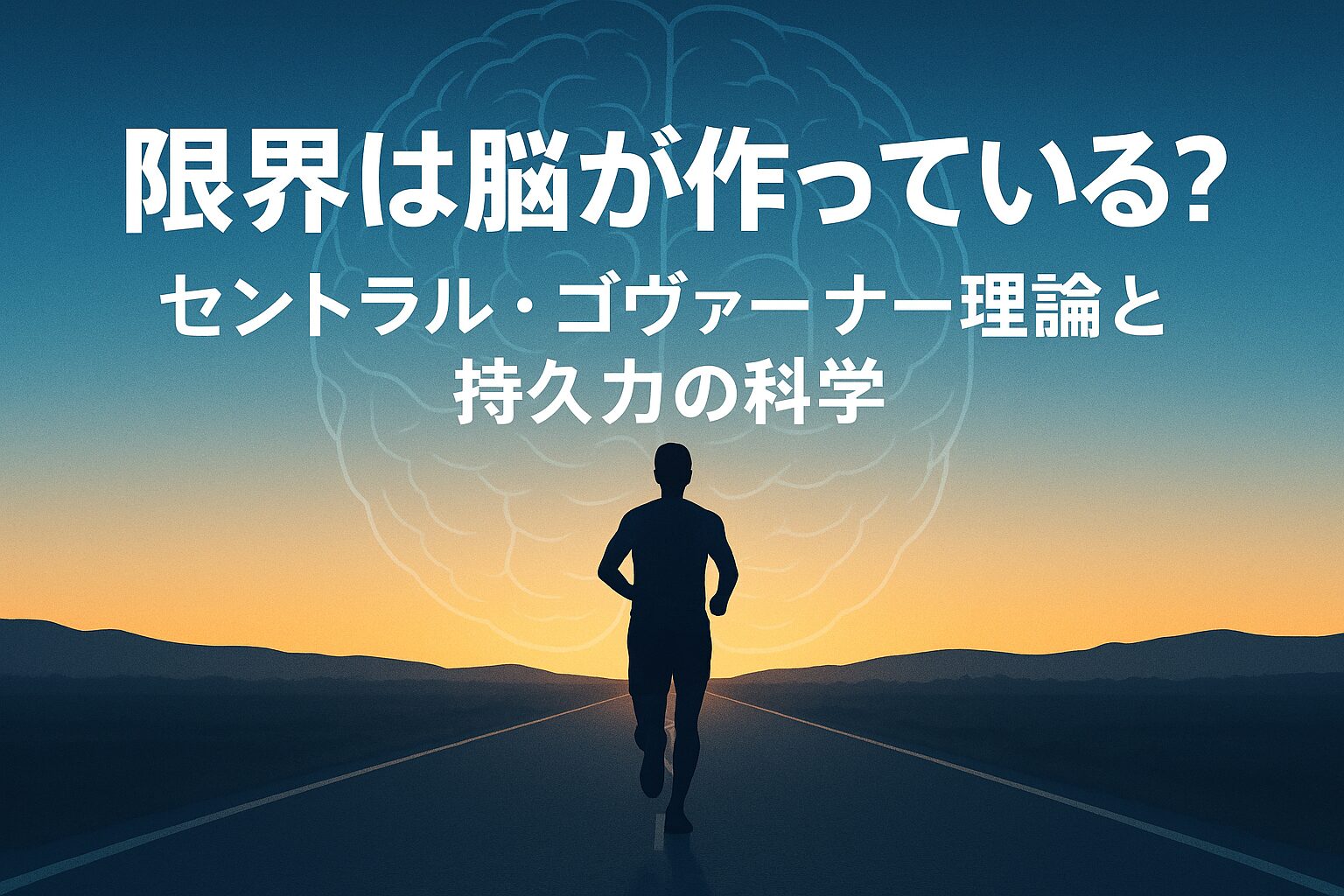

コメント