ランニングにはLSD(ロングスローディスタンス)やインターバル、テンポ走など多様なトレーニング法がありますが、意外と見落とされがちなのが「アクティブレスト(積極的休養)」です。
しかしこのアクティブレスト、実は上級者ほど意識的に取り入れており、コンディション調整・疲労抜き・怪我予防・パフォーマンス向上に欠かせないメソッドです。
この記事では、科学的根拠と実践例に基づき、「アクティブレストとは何か」「なぜ必要か」「どう実施すればよいか」をランナー向けに徹底解説します。
1. アクティブレストとは何か?
アクティブレストとは「積極的休養」と訳され、文字通り「軽い運動を通して回復を促進する」休養のことです。
完全休養(パッシブレスト)が文字通り「休むこと」に重点を置くのに対し、アクティブレストは「適度に身体を動かすこと」で血流を促進し、疲労物質の除去や筋肉の回復を助けます。
競技者だけでなく市民ランナーや健康目的のランナーにも、週に1回以上取り入れることが推奨される「疲れを溜めずにトレーニングを継続するための知恵」と言えるでしょう。
2. ランナーにとってなぜ必要か?
- 疲労物質の代謝促進:軽度の有酸素運動により血流が促進され、筋内の老廃物(乳酸など)の除去が進みます。
- 筋損傷の修復:ミクロレベルの筋損傷の修復に必要な酸素と栄養を届けやすくします。
- DOMS(遅発性筋肉痛)の緩和:ストレッチや低強度の運動で筋膜の癒着や張りを解消。
- オーバートレーニング防止:精神的・身体的に過剰な負荷を回避し、継続可能なトレーニングを支えます。
- 自律神経の調整:交感神経に傾いた体を副交感神経優位に戻し、睡眠の質や消化の改善にも寄与します。
3. アクティブレストと運動強度の関係
アクティブレストの効果を最大化するには、「どれくらいの強度で行うか」が最も重要です。
一般的に目安とされるのが以下の基準です:
- 心拍数:最大心拍数(HRmax)の50〜60%
- RPEスケール:2〜3(非常に楽〜楽)
- 会話テスト:息が切れずに会話できる強度
■ HRmaxに基づく心拍ゾーン例(目安)
| 年齢 | HRmax(推定) | アクティブレスト心拍数 |
|---|---|---|
| 25歳 | 195 | 98〜117 bpm |
| 35歳 | 185 | 93〜111 bpm |
| 45歳 | 175 | 88〜105 bpm |
「スロージョグ」といっても、キロ6で心拍110の人もいれば、キロ9でも心拍130を超える人もいます。大事なのはペースではなく「心拍数ベース」での管理です。
4. 気温・湿度とアクティブレスト:なぜペースではダメなのか
気温や湿度が高い日は、体温調節のために心拍数が大きく上昇し、同じキロ6でも身体への負荷は2割以上増すことがあります。
つまり、普段なら回復ペースでも、その日の気象条件では「追い込み強度」になってしまっていることがあるのです。
■ 気温・湿度別のペース調整例(同じHRmax 180のランナー)
| 条件 | いつもの回復ペース | 実際の心拍 | 調整後ペース |
|---|---|---|---|
| 20℃・湿度40% | キロ6 | 105bpm | キロ6でOK |
| 30℃・湿度70% | キロ6 | 125bpm | キロ7〜8 |
| 35℃・湿度80% | キロ6 | 135bpm | 中止 or 室内バイク |
このように、環境変化に対応するためにはペースではなく「心拍数基準」が最も安全かつ効果的です。
5. 具体的なアクティブレストの方法(ランナー向け)
■ 外でできるアクティブレスト
- ウォーキング(30〜40分)
- スロージョグ(HR120未満で20〜30分)
- サイクリング(軽負荷ギアで20〜30分)
■ 室内・代替手段
- エアロバイク(冷房下で心拍制御しやすい)
- ヨガ・ストレッチ(特に太腿・ふくらはぎ・股関節)
- ラジオ体操・動的ストレッチ
■ 注意点
- 「楽すぎるかな?」くらいでちょうど良い
- 筋肉痛が強い箇所は無理に動かさない
- 暑すぎる日は屋内へ切り替えよう
6. 実践例:ランナー別のアクティブレスト戦略
| ランナーレベル | 内容 | 心拍数目安 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 初心者 | 散歩+軽いストレッチ | 90〜105 bpm | 20〜30分 |
| 中級者 | キロ8〜9ジョグ+動的ストレッチ | 100〜110 bpm | 30〜40分 |
| 上級者 | キロ6〜7ジョグ+軽ドリル | 105〜115 bpm | 40〜50分 |
アクティブレストも「目的と状態に応じた個別化」が重要です。
7. よくある誤解とNG例
- 「疲労抜きジョグ」でゼーハーしている:心拍150超ではそれはもうトレーニングです。
- 「いつものペース=回復」思考:気温や疲労によって同じペースでも負荷は変わる。
- 休養日に毎回30km走をしてしまう:回復しないまま次の週に突入する負のスパイラル。
8. まとめ:アクティブレストは“心拍数で考える時代”へ
アクティブレストは単なる「サボり」ではありません。むしろ賢いランナーが取り入れる積極的戦略です。
気温やペースではなく、その日の「心拍数」や「感覚」に合わせて強度を調整することで、身体はより早く回復し、次のトレーニングにもつながります。
「何をしないか」ではなく、「どう動くか」を考える——それが現代のアクティブレストです。
参考文献
- Mika A et al. (2007). Comparison of two types of active recovery on lactate removal following maximal exercise. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness.
- Reilly T & Ekblom B. (2005). Recovery from exercise: current knowledge and implications for future research. Journal of Sports Sciences.
- 日本スポーツ協会「リカバリーの重要性と方法」

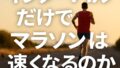
コメント