はじめに:なぜペース設定で失敗するのか
フルマラソンでは、目標タイムを決めること自体は悪いことではありません。むしろ多くのランナーにとって、それがモチベーションになります。しかし問題は、「理想の数字」に走力を合わせにいってしまうことです。この章では、多くのランナーがなぜペース設定で失敗するのかを整理し、現実的な基準の必要性を示します。
人間の体はコンディションや環境によって大きく変化します。睡眠不足、前日の食事、気温や湿度、そして練習の積み重ね――これらが複雑に絡み合うため、必ずしも「想定したペース=当日の適正ペース」ではありません。このギャップを無視すると、「前半は快調」でも「後半に地獄」が待っています。つまり、マラソンは「距離」そのものよりも「自分の身の丈に合わないペース設定」で失敗するケースが圧倒的に多いのです。
オーバーペースの弊害と科学的エビデンス
マラソンで失速する最大の原因は、序盤からのオーバーペースです。この章では、オーバーペースがもたらすエネルギー的・生理的なリスクについて、研究データを交えて解説します。
オーバーペースは体力的な消耗だけでなく、心理的な打撃も大きいものです。30km以降に失速すると「もうダメだ」「なぜ自分だけ苦しいのか」という思考に陥り、ペース維持の意志すら難しくなります。つまりオーバーペースは「体を壊す」だけでなく「心を折る」リスクを抱えているのです。
グリコーゲン枯渇と「30kmの壁」
「30kmの壁」と呼ばれる現象は、単なる比喩ではなく科学的な根拠があります。人間の体内に蓄えられる糖質(グリコーゲン)は限られており、速すぎるペースではその消費が加速し、30km付近で枯渇します。その瞬間からエネルギー供給の主役は脂質に切り替わりますが、脂質は糖に比べてエネルギー化に時間がかかるため、ペースを維持できなくなります。
Coyle et al. (1983)の研究では、グリコーゲン枯渇時に運動継続能力が劇的に低下することが報告されました。つまり「壁」とは意志の弱さではなく、燃料切れという生理現象なのです。
筋損傷と回復遅延
また、オーバーペースは筋損傷のリスクを高めます。速すぎる動きは着地衝撃を強め、特に大腿四頭筋などのエキセントリック収縮を伴う筋群に強いダメージを与えます。Nielsen et al. (2012)の研究では、過大なペース設定によってマラソン後の筋損傷指標(CK値)が顕著に上昇することが示されました。これは「その日の失敗」だけでなく、「次の練習や大会への影響」という形で長期的なデメリットにもつながります。
正しいレースペースの決め方:段階的アプローチ
では、どうやって適正なペースを導くべきでしょうか。この章では、レースタイムや練習データを活用した段階的なアプローチを紹介します。
実力の把握:過去レースやVDOTを活用
5kmや10km、ハーフの記録からフルの走力を推定するのは有効です。Jack DanielsのVDOT指標やMcMillanの計算式はその代表例で、理論的な「上限ペース」を把握することができます。
例:10kmを45分で走るランナー → VDOT約50 → フル換算3時間30分(5:00/km)。ただし、これは理想条件下での「上限値」にすぎません。
🫀 心拍数によるペース設定の重要性
ここでは、心拍数を用いたペースコントロールの有効性について解説します。心拍はその日の体調や環境を即座に反映するため、非常に信頼性の高い指標です。
心拍は「その日の現実」を映す
VDOTや過去のレース記録が示すのは「理論上の走力」ですが、心拍は体調、睡眠、気温、湿度、疲労などをリアルタイムで反映します。心拍を見れば、そのペースが本当に持続可能かどうかが分かるのです。
理想的な心拍ゾーン:HRmaxの85〜88%以内
フルマラソンにおける理想的なゾーンは、最大心拍数の85〜88%以内。この範囲を超えると糖質依存が強まり、後半に失速します。
| ゾーン | 心拍割合 | 状態 |
|---|---|---|
| 〜80% | イージー | 脂質代謝中心、会話可能 |
| 80〜88% | マラソン最適域 | ややきついが持続可能、糖+脂質併用 |
| 88%超 | LT域以上 | グリコーゲン消費過多、持続困難 |
気象条件と心拍の関係
気温や湿度が高い日は、同じペースでも心拍が10〜15拍高く出ることがあります。その場合は「予定のペース」で走ると実質的にはオーバーペースとなり、早期に失速します。したがって、「ペース」ではなく「心拍」に基づいて修正する柔軟性が必要です。
心拍と主観(RPE)の組み合わせ
心拍計は便利ですが、ノイズや誤差もあります。そこでRPE(主観的運動強度)と心拍を併用するのがベストです。「ややきついが会話可能=RPE12〜13」で、その時の心拍がHRmax85%未満であれば適正ペースといえます。心拍とRPEを組み合わせることで、数字と感覚の両面から精度の高いペース判断が可能となります。
VDOTは「上限の目安」、実戦では下方修正が前提
Jack Danielsが提唱したVDOTは優れたモデルですが、気温10℃、無風、フラット路面という理想条件を前提にしています。したがって実際のレースでは必ず補正が必要です。この章では、VDOTを下方修正すべき理由とその方法を解説します。
- 気温が25℃なら+5〜10秒/km
- 累積上昇200mなら+20秒/km
- 風速4m/s向かい風なら+10秒/km
VDOTを活用する際は、これらの補正を行い「現実的なペース」を設定することが成功の条件となります。
動的なペース戦略のすすめ
マラソンでは「同じペースで押し通す」よりも、状況に応じて調整することが成功の鍵です。この章では、ネガティブスプリットを含めた動的な戦略について解説します。
- 序盤(〜5km):楽すぎるくらいのペースで。HRmaxの80〜85%
- 中盤(10〜30km):補給や心拍を確認しつつ淡々と維持
- 終盤(30km以降):余力があればペースアップ
このように「動的ペース戦略」を取ることで、後半の失速を防ぎ、結果的に良い記録につながります。
失速の典型事例と学び
ここでは、実際に多くのランナーが経験する失速例を紹介します。
目標:サブ3.5(4:55/km設定)
実力:10km46分(理論上3:33〜3:35)
気象:22℃、アップダウンあり
→ 25km以降失速、30kmから5:30/kmまで落ち込み、3:45でゴール
この例は「理論値に固執し、心拍による修正を怠った」典型です。逆に心拍基準でペースを5:10/kmにしていれば、後半に粘って3:40以内で走れた可能性が高いのです。
まとめ:現実対応力こそ最強の武器
最後に、この記事の要点をまとめます。
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| VDOTは上限 | 現実には気象・地形で補正が必須 |
| 心拍基準 | HRmaxの85〜88%以内が理想ゾーン |
| スタートの抑制 | 「楽すぎる」と感じるくらいで入る |
| 成功の鍵 | ペースではなく、心拍と体感で走る勇気 |
参考文献
- Coyle, E. F., et al. (1983). “Muscle glycogen utilization during prolonged strenuous exercise when fed carbohydrate.” Journal of Applied Physiology
- Ely, M. R., et al. (2007). “Effect of ambient temperature on marathon performance.” Medicine & Science in Sports & Exercise
- Daniels, J. (2005). Daniels’ Running Formula
- Nielsen, H. B., et al. (2012). Skeletal muscle damage and repair in marathon runners
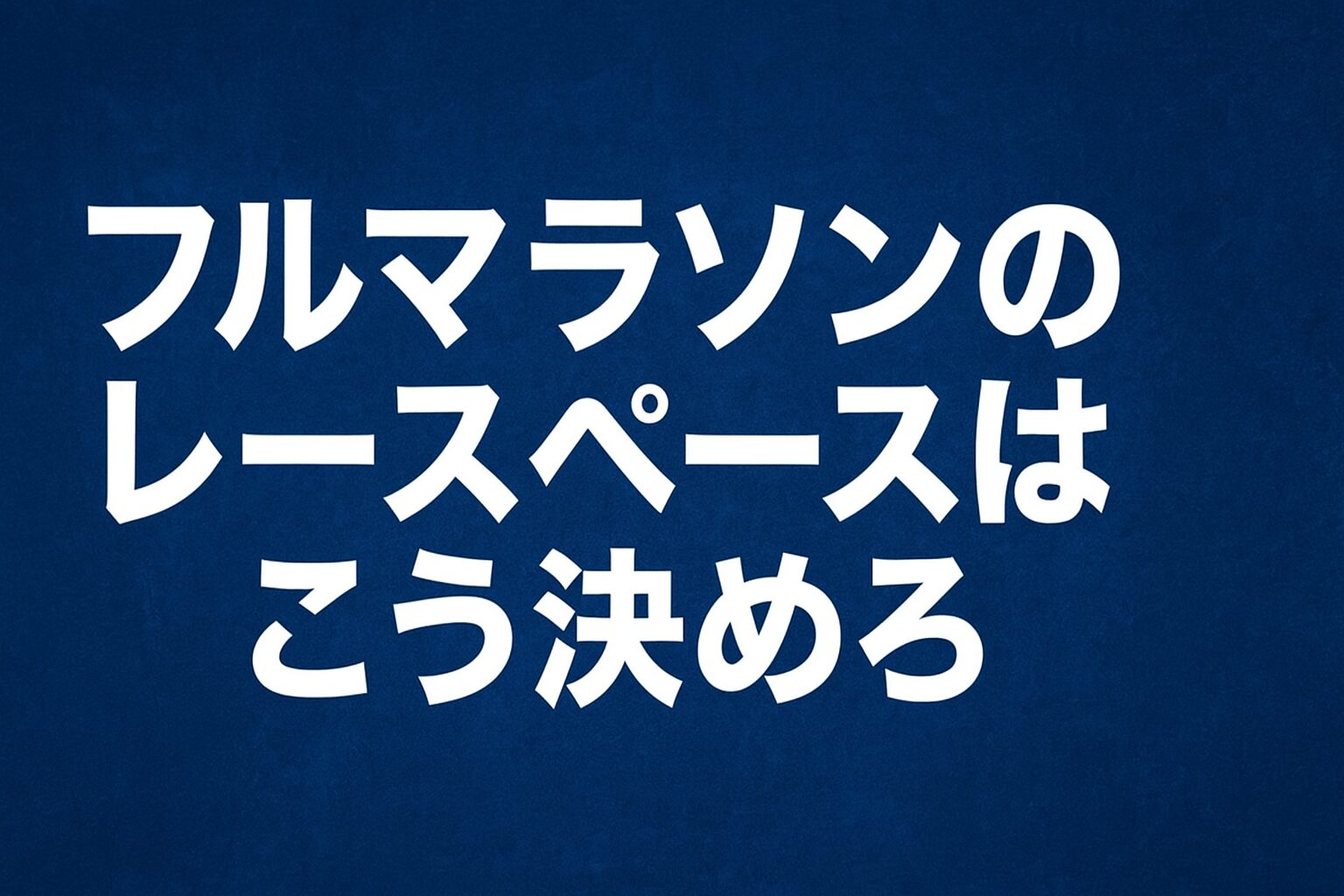


コメント