導入:なぜLSDは軽視されがちなのか
ランニング界で「LSD(Long Slow Distance)」という言葉を知らない人はいないでしょう。
「ゆっくり長く走る練習」として、多くの書籍や雑誌に登場します。しかし一方で、インターバル走やビルドアップ走といった「強い練習」に比べると、地味で成果が見えにくいため軽視されがちです。
実際、SNSやランニングクラブで話題にされるのは、速いペース走やレースシミュレーション練習ばかり。LSDは「初心者向け」「時間のある人がやるもの」と誤解されることさえあります。
しかし、これは大きな間違いです。
LSDこそがマラソン後半の粘りを生み出す“土台”であり、ウルトラマラソンのような超長距離を走るランナーの身体を形づくる基盤なのです。
本記事では、まずLSDの正しい定義と効果を整理し、そのうえで 「LSDを抜いた場合の弊害」、さらに 「ウルトラランナーとマラソンランナーの身体的比較」 を通して、なぜLSDが不可欠なのかを徹底的に解説します。
LSDとは何か?──定義と誤解
LSD(Long Slow Distance)は、文字通り「長く・ゆっくり・距離を走る」練習です。
- Long(長く):少なくとも60分以上。理想は90〜150分。上級者なら3時間走もあり得る。
- Slow(ゆっくり):最大心拍数の60〜70%。会話できる程度の強度。
- Distance(距離):距離を基準にするのではなく、「走行時間」で考える。
よくある誤解
- 「ペースが遅ければLSD」 → 実際には速すぎるケースが多い。
- 「90分走ったからLSD」 → 心拍ゾーンが高ければただのロング走。
- 「フォームは気にしなくていい」 → 長時間走るからこそ姿勢が崩れ、故障リスクが増す。
LSDの本質は、“楽に会話できる強度で、長時間走り続けること” です。
LSDの科学的効果
LSDが地味ながらも重要な理由は、身体の根本的な適応を引き出す練習だからです。以下の5つが代表的な効果です。
1. ミトコンドリア増加と有酸素能力向上
低強度で長時間走る刺激は、筋細胞内のミトコンドリアの数と機能を増加させます。ミトコンドリアは「エネルギー工場」であり、酸素を使って脂肪や糖からATPを作り出す役割を担います。
ミトコンドリア密度が高いほど、酸素利用効率が上がり「長く走れる体」に。
📖 Holloszy & Booth (1976)
2. 毛細血管の新生
LSDは筋肉内の毛細血管網を拡張し、酸素や栄養の供給効率を改善します。
血流改善により、疲労物質の除去やリカバリー能力も高まる。
📖 Andersen & Henriksson (1977)
3. 脂質代謝の促進
長時間の低強度運動は、脂肪をエネルギーに変換する酵素群(脂肪酸酸化酵素)を活性化します。
糖(グリコーゲン)に依存せず、脂質を有効活用できる → 「30kmの壁」を突破。
📖 Romijn et al. (1993)
4. 筋・腱・関節の耐久性強化
「同じ動きを何時間も繰り返す」刺激は、速いペースでは得られないフォーム維持力や腱・靭帯の耐性を育てます。
5. 精神的スタミナ
単調な時間を走る経験は、集中力・我慢強さ・メンタル耐性を養います。フルマラソンやウルトラの終盤で「心が折れない力」になります。
LSDを入れない場合の弊害
「LSDを省いても、スピード練習や閾値走をしていれば強くなるのでは?」と考える人もいるでしょう。
しかし、LSDを抜くと以下の弊害が現れます。
- レース後半の失速:脂質代謝能力が育たず、糖に依存 → 30km以降にガス欠。
- 心肺の“持久耐性”不足:インターバルで心肺は強化されても、安定した低強度を維持する力が不足。
- 脚の耐久性不足:フォームを長時間維持できず、脚が止まる。
- 慢性疲労・オーバートレーニング:高強度偏重になり、疲労が抜けず怪我のリスクが増大。
- 精神的な弱さ:単調さに耐える経験が不足 → 長距離レースで集中力が切れやすい。
ウルトラランナーとマラソンランナーの身体的比較
ここからが本題です。ウルトラランナーはマラソンランナーと何が違うのか?
1. エネルギー利用の違い
- マラソンランナー:主に糖と脂肪をミックス燃料として利用。後半は糖が枯渇 → 「30kmの壁」。
- ウルトラランナー:糖依存を大幅に下げ、脂肪代謝を主体に走る。長時間でも安定したペースを維持可能。
📖 Achten & Jeukendrup (2004)
2. 筋線維タイプの違い
- マラソンランナー:速筋線維(Type IIa)も動員し、スピード耐性が高い。
- ウルトラランナー:遅筋線維(Type I)が優位 → 省エネ効率が非常に高い。遅筋は脂肪を燃料にでき、疲労耐性も強い。
3. ミトコンドリア・毛細血管の発達度
ウルトラランナーは長時間走を繰り返すため、ミトコンドリア密度・毛細血管網が顕著に発達。
「低出力を長時間維持する能力」が極端に強化される。
4. 実際の観察データ
研究では、ウルトラランナーは同レベルのマラソンランナーよりも脂質代謝能力(Fatmax:脂肪燃焼が最大になる強度)が高いことが確認されています。
マラソンランナー:Fatmaxは概ねVO₂maxの45〜55%。
ウルトラランナー:Fatmaxは60%以上にシフト → より速いペースでも脂肪利用可能。
5. レース戦略上の違い
- マラソン:糖をどう節約するかがテーマ。
- ウルトラ:最初から最後まで脂質代謝主体 → LSD的な走りそのものが勝敗を分ける。
LSDとウルトラの接点
- マラソンにおけるLSD:糖を温存し、30km以降も粘れる力をつける。
- ウルトラにおけるLSD:レース全体が脂質代謝ゾーンなので「LSD能力」がそのまま完走力。
つまり、ウルトラランナーのような「燃費のいい身体」を作る過程にこそ、フルマラソンの完走力向上のヒントがあるのです。
LSDを実践するための具体例
- 頻度:週1回
- 時間:90〜150分(上級者は180分)
- 心拍数:最大心拍数の60〜70%
- 補給:90分を超える場合はジェル・電解質飲料必須
- コース:信号が少なく、フォームを崩さずに走れる環境
まとめ
LSDは「地味なジョグ」ではありません。
- ミトコンドリア・毛細血管の発達
- 脂質代謝の強化
- 筋・腱・関節の耐久性
- 精神的持久力の養成
さらに、ウルトラランナーが示す脂質代謝に優れた身体構造は、LSDの積み重ねによって築かれるものです。
マラソンランナーにとってもLSDは「ウルトラ的な燃費性能を部分的に取り入れる」練習であり、30km以降の失速を防ぎ、最後まで走り切る力を支えます。
強度練習だけでは“短期的なスピード”しか育ちません。
長期的な持久力の根幹を育てるのは、LSDという地味な積み重ねなのです。
参考文献
- Holloszy, J. O., & Booth, F. W. (1976). Biochemical adaptations to endurance exercise in muscle. Annual Review of Physiology.
- Andersen, P., & Henriksson, J. (1977). Capillary supply of the quadriceps femoris muscle of man: adaptive response to exercise. The Journal of Physiology.
- Romijn, J. A., et al. (1993). Regulation of endogenous fat and carbohydrate metabolism in relation to exercise intensity and duration. Am J Physiol.
- Achten, J., & Jeukendrup, A. E. (2004). Fat metabolism during exercise: a review. International Journal of Sports Medicine.
- Knechtle, B., & Nikolaidis, P. T. (2018). Physiology and pathophysiology in ultra-marathon running. Frontiers in Physiology.
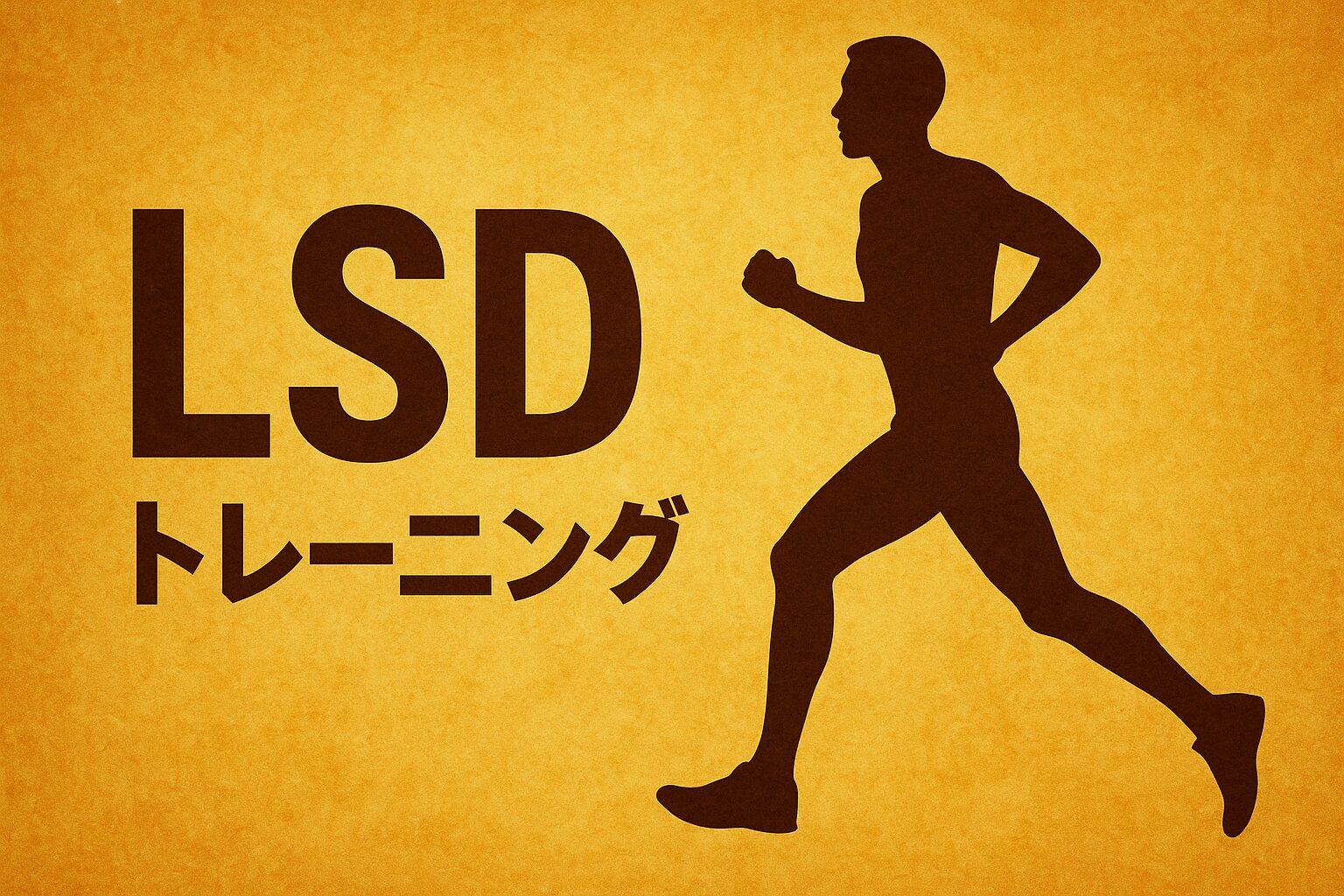

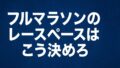
コメント