LSD(ロング・スロー・ディスタンス)は、市民ランナーにとって持久力を高めるための定番トレーニングです。低い心拍数で長時間走ることで、毛細血管やミトコンドリアの発達、脂質代謝能力の向上といった有酸素的な適応を得られます。
しかし、ランニングを始めたばかりの初心者が、書籍やネットで推奨される「最大心拍数の60%前後」を守ろうとすると、「歩くくらいのペース」になってしまうことがあります。
このとき、次のような疑問や不安を感じる方も多いでしょう。
- 「歩いてしまったらLSDにならないのでは?」
- 「走る刺激が入らないと意味がないのでは?」
- 「それなら最初から歩いたほうがいいのでは?」
この記事では、初心者ランナーがLSDを行う際の歩きになる問題について、トレーニング原則・生理学的背景・実践的解決策を交えて解説します。さらに、アメリカのランニングコーチ、ジェフ・ギャロウェイ氏が提唱したウォークブレイク戦略を活用したLSDの具体的な方法も紹介します。
なぜ初心者はLSDが歩きになるのか?
ランニングを始めたばかりの方は、有酸素能力や心肺機能がまだ発達途上です。特にランニングフォームが安定していない段階では、わずかなペースの上昇でも心拍数が急上昇しやすくなります。
例えば、最大心拍数(HRmax)が180の人の場合、LSDの推奨ゾーンである60%はおよそ108拍/分です。初心者がこの数値を守ろうとすると、ジョギングよりもウォーキングに近い動きになってしまうことがあります。
走りと歩きの生理的な違い
- ランニングは「浮き足」の瞬間があり、着地衝撃が大きい
- ウォーキングは常に片足が接地しており、衝撃が小さい
- ランニングでは大腿四頭筋・ハムストリングス・腓腹筋などが強く動員される
- 歩行では臀筋群や脊柱起立筋の関与が相対的に大きい
つまり、ウォーキングではランニング特有の筋肉の使い方や衝撃耐性が鍛えられにくく、特異性の原理の観点からも「ランニング能力を高める刺激」としては不足しやすいのです。
特異性の原理とLSDの意味
トレーニング理論における特異性の原理(Specificity Principle)とは、「運動の効果は、その運動様式・筋群・エネルギー供給系に特異的に現れる」という考え方です。
持久力を伸ばすには、ランニングという動作そのものを一定時間続ける必要があります。これは単に心拍数や呼吸を一定に保つだけでなく、フォーム維持や着地衝撃への適応、筋持久力の向上といった複合的な適応を伴います。
初心者でも「LSD=ランニング動作を伴った低強度長時間走」という枠組みは意識したほうが効果的です。
完全ウォークでは不足するが、完全ランも難しい
初心者が心拍数を守ろうとすると完全に歩きになる。一方で、ずっと走ろうとすると心拍数が上がりすぎてLSDの領域を外れる――。このジレンマを解消する方法として、近年市民ランナーの間で注目されているのがウォークブレイク戦略です。
ウォークブレイク戦略とは?
ウォークブレイクは、アメリカの元オリンピック選手でコーチのジェフ・ギャロウェイ(Jeff Galloway)氏が提唱したランニングメソッドです。走る時間と歩く時間を意図的に組み合わせ、長時間・低負荷での持久力養成や疲労軽減を狙います。
ギャロウェイ氏は、この方法により初心者からベテランまで多くのランナーがケガを減らし、フルマラソン完走率を高めたと報告しています。
ウォークブレイクの基本的なメリット
- 心拍数をコントロールしやすい
- 筋肉・関節への負担を軽減できる
- 長時間練習に伴う精神的疲労を減らせる
- 初心者でも安全に距離を伸ばせる
初心者向けウォークブレイクLSDのやり方
初心者がLSDでウォークブレイクを活用する場合の例を紹介します。
時間ベースの方法
- ラン3分+ウォーク1分を繰り返す
- ラン5分+ウォーク1分など、徐々にラン区間を延ばす
距離ベースの方法
- 1kmラン+200mウォークを繰り返す
- ラン区間の距離を伸ばし、歩き区間を短くしていく
心拍数ベースの方法
- 走ってHRmaxの65%を超えたらウォーク
- HRが60%に下がったら再びラン
効果を高めるためのポイント
- ラン区間でペースを上げすぎない(フォームが崩れる原因)
- 歩き区間もだらけすぎない(リズムを維持)
- トータル時間を優先(距離にこだわらない)
- 定期的な心拍確認(ランニングウォッチやチェストストラップ)
初心者からのステップアップ例
- 初期:ラン3分+ウォーク2分で60分
- 中期:ラン5分+ウォーク1分で90分
- 後期:ラン10分+ウォーク1分で120分
このように、走る割合を少しずつ増やしながら全体時間を延ばすことで、徐々に「走りっぱなしのLSD」に移行できます。
ウォークブレイクLSDの落とし穴
便利な手法ですが、注意点もあります。
- 歩き区間でスマホをいじるなど集中が切れる
- 歩きが長くなりすぎて刺激不足になる
- ラン区間が短すぎてフォームづくりの効果が得られない
上級者ランナーがウォークブレイクを使うケース
ウォークブレイクは初心者専用の手法ではありません。むしろ、フルマラソン3時間台やウルトラマラソン完走者など、上級者ランナーが戦略的に導入する例も多くあります。
1. ウルトラマラソンでのペースコントロール
100kmやそれ以上の距離を走るレースでは、序盤から走り続けると終盤に大きく失速するリスクがあります。上級者の中には、あえて序盤から「エイドごとに1分歩く」「20分走って1分歩く」などのウォークブレイクを入れ、筋疲労の蓄積をコントロールする戦略を取る人がいます。
2. 暑熱環境での体温管理
夏のレースや高温下の練習では、走り続けることで体温が上がりすぎる危険があります。ウォークブレイクを活用することで心拍数と体温を下げ、熱中症リスクを減らすことができます。
3. 記録狙いのマラソンでも有効な場合
ジェフ・ギャロウェイ氏自身は、ウォークブレイクを使ってサブ3(3時間切り)を達成した例を紹介しています。一定間隔で短い歩きを入れることで、後半のペースダウンを防ぎ、平均ペースを高く維持することが可能になります。
4. 怪我からの復帰期の距離確保
怪我明けのランナーが練習量を戻す際に、ウォークブレイクを入れることで衝撃や負担を減らしながら距離を踏むことができます。これにより、故障リスクを抑えて持久力の回復が可能になります。
5. 精神的リズムの維持
長時間走では、単調さによる集中力低下やメンタルの疲労がパフォーマンス低下の原因になります。ウォークブレイクを区切りとして使うことで、「次のラン区間まで頑張る」という短期目標の積み重ねができ、精神的に楽になります。
このように、ウォークブレイクは「初心者のための妥協策」ではなく、トップランナーも活用する戦略的ペーシング法です。目的や状況に応じて、初心者から上級者まで幅広く使える汎用性の高い手法と言えます。
まとめ:歩きを恐れず、目的に沿ったLSDを
初心者がLSDで歩きになるのは自然なことです。重要なのは「走らないと意味がない」と決めつけるのではなく、低強度で長時間動き続けることによる有酸素的刺激をどう確保するかです。
ウォークブレイクを活用すれば、初心者でも安全に、かつ効果的に持久力を養えます。走力がついてきたら、歩き区間を減らしていけば、やがては本来の「ランニングLSD」へ移行できるでしょう。
歩きを恐れず、賢く使うこと。それが初心者ランナーのLSD成功のカギです。
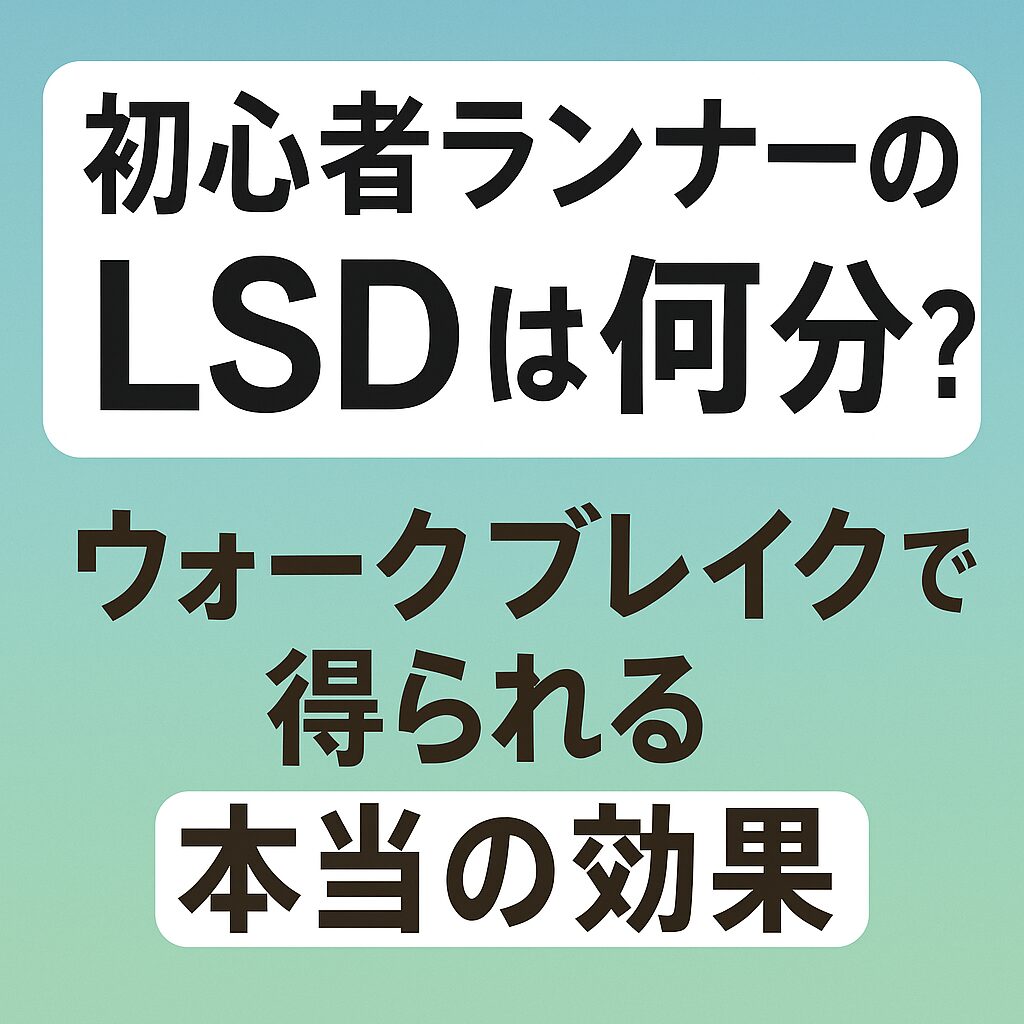

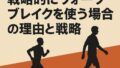
コメント